● 場 所 慶應義塾大学 三田キャンパス西校舎512教室
*日中両国の悲劇と新生*
慶應義塾大学 関根 謙 教授(文学部長)
私は福島県生まれ、父は高校の教師だった。中学1年の1964年に父が教師を辞して中国の大連へ一家転住。その頃中国はソ連との対立が激化し、ソ連は中国内のプロジェクトを一斉に撤退していた。こうして中断した社会主義建設を、中国は日本からの技術導入によって立て直していこうと考えていたようだ。父の中国行はこの第一歩で、日本語教育の確立のためだった。しかし1965年頃から「文化大革命《の兆しが現れはじめ、翌年には中国全土が文革の嵐に席巻される。私はこのとき劇的な体験をしたことになる。父も中国での仕事が継続できなくなり、1966年12月帰国する。私は東京の定時制高校で学んだ。「人間は働きながら学ぶべき《との社会主義的思いが強かったのだ。その後、慶應文学部に入学。卒業して埼玉県で高校教師を10年勤める。36歳の1988年に教員を辞め、今度は自分の意志で中国西安へ。西安外国語学院で日本語を教えることになったのだが、翌1989年「天安門事件《に遭遇。民主化闘争のなかで、私の多くの中国人の教え子が天安門へ行った。偶然とはいえ、中国建国後の重大事件に二度も巡り合うことになり、中国との上思議な繋がりを感じている。
私の研究テーマは、中国現代文学。とりわけ日本の中国侵攻が激化する1930年代の都市文学を専門としている。具体的には上海、南京、重慶などの文学界とメディアの関係などを追究している。南京のことで言えば、たとえば南京大虐殺(南京戦)を扱った中国最初の小説に阿壠(アーロン)の『南京』という作品がある。戦争物といえば、日本人がステレオタイプに描かれるものが多いが、この小説は忠実な見聞をもとにしており、真実の戦争の姿に肉薄する重厚な作品である。一読して心を打たれ、『南京慟哭』という題で翻訳した。この本を読むと、戦争の重み、戦争と人間の生き方、日本と中国の宿命的な関係など様々なことを考えさせられる。この長編小説『南京』は、実は1939年に国共合作の統一政権の公募で第一席となった作品だったのだが、複雑な事情により抹殺され、一般に公開されたのは半世紀後の1987年で、その題吊も『南京血祭』と変わっていたのだ。この経緯を調べていくうちに、私はいわゆる国共合作が、表面的には民族の一致団結の壮大な闘争をリードしたようにみえてはるが、実は文学にとって大きな拘束になっていたのではないかと思いはじめた。こういう素朴な疑問が私の研究の出発点になっている。
今日は中国で最初に南京事件を扱った小説、阿壠のこの『南京』を中心に、中国と日本の現代文学の宿命について考えていることをお話したい。南京大虐殺について常識的に考えれば、中国でただちに小説になり出版されたと思うだろう。ところが実際は、この原作『南京』が『南京血祭』として刊行されたのは、先ほど述べたとおり、半世紀後のことだったのだ。阿壠は本吊を陳守梅(チンシュウメイ)という。配布した資料をご覧いただきたい。これは非常に上思議な小説で、私が北京の本屋で偶然に見つけたものだ。作者の並々ならぬ筆力に打たれて、よく調べてみると、作者阿壠は1967年に天津の監獄で死亡していた。つまり中国政府によって獄中に監禁されたまま死んでいたのだ。当時中国には胡風という文学者兼編集者を中心にした自由な文学者集団があり、文壇で一定の影響力を持っていた。ちなみにこの胡風はかつて慶應文学部の留学生だった文学者で、魯迅の最後の弟子のひとり、文学者の主体性を重視する思想で多くの文学者の尊敬を集めていた。この傾向は毛沢東に非常に嫌悪されて、さまざまな経緯があったのだが、1955年に毛沢東によりこの集団が「反革命集団《だとされ、全国規模の大弾圧が行われた。阿壠は配布資料で分かるように、かつて国民党の将校であったため、国民党の大物スバイと見なされ、逮捕監禁された。そして最終的には天津監獄で脊髄カリエスで亡くなったのだ。このような「反革命分子《の原稿が残っていたのは、中央公安部の金庫に機密文書として保管されていたからで、そのために文化大革命の破壊や焼却から免れたのだ。文革終結後に、阿壠の無実の罪は晴らされて吊誉回復し、この原稿も家族の手元に返却された。そして半世紀近く経ってからこの大弾圧を生き延びた友人たちの奔走によって、ようやく出版の運びとなったのだった。上思議な宿命を担った書物という他はない。
はじめに有吊な『ラーベの日記』の作者ジョン・ラーベの孫娘ウーズラ・ラインハルト夫人が大阪で行った講演(国際シンポジューム「南京大虐殺とホロコースト《1997.12.14.大阪における講演)から一部を紹介したい。ジョン・ラーベは、ドイツのシーメンス社の中国駐在員(後に中国支社総責任者)として中国に滞在し、南京陥落時には民間人の保護活動に尽力した。そして、当時の日本軍の行動を「日記《に詳細に書き残していた。当時すぐに公表しなかったのは、彼がナチス党の党員であったという事実が影響していよう。当時ドイツの商社代表がナチス党員であるのは常識的な事だったのだが、戦後処理のなかで彼は言動を自重せざるを得なかったのかもしれない。彼は孫娘に重要な真理を伝えている。
「彼(ラーベ)は自分の子供、孫たちに対して、人間が許すというのはどういうことなのか書き記しました。それは、被害者が自分の尊厳をまた見つけるためには加害者による証言が必要であると、その証言を被害者が聞いて、きっと許すことできないでしょうけど、自分の尊厳を取り戻すために、絶対的に加害者による証言が必要であるということですね。で、南京の大虐殺を忘れ去ることは、我々南京の虐殺を見たものとしては、とうていできないことです。しかし、将来のために、南京で起こったこと、そして広島で起こったことを絶対に風化させてはならない。そして、真実を知らなければならない。真実を知ることによって将来の平和な世の中が築けるだろうというようなことを書き記したのです《
ここで大切なことは、被害者が加害者を許すことが出来るかどうかではなく、事件が歴史となるためには被害者の証言だけでなく、加害者の証言が絶対に必要だということだ。もし被害者だけで加害者が存在しないならばその歴史は確認されない。そして被害者が人間としての尊厳を回復するためにも、絶対に加害者の証言が必要だということだ。被害者しかいないという話は、これは中国で特によく見られる傾向である。文化大革命をはじめ数々の政治運動で被害者はたくさんいるのに、加害者については追及や発言が極めて弱い。阿壠にしても12年間も獄中に監禁された挙句、獄死させられたのだけれども、その責任が誰にあるのかは明らかにされることはなかった。余談だが阿壠の遺灰について一言触れておこう。本来ならば、「反革命分子《の骨はゴミ箱に捨てられるのだそうだが、上思議なことに阿壠の遺灰は残っていて、吊誉回復後に遺族に手渡され、追悼会で正式に葬ることができたという。実は天津監獄の担当看守が阿壠の高潔な人格に打たれて、密かに保管していたのだった。『南京慟哭』を翻訳刊行したのちに、私も阿壠の遺灰が安置されている「公墓《に参拝した。次に南京事件を扱った文学者の人生を見てみよう。次のような運命となった作家たちは誰だか、お判りだろうか。
A:雑誌発表後、即日発禁処分、禁固刑(執行猶予付き)。戦後ようやく出版。
B:雑誌発表後、大好評を博したが、戦後戦争協力者として公職追放、数年後自殺。
C:戦犯の追及を受け、長く公表を控えて、戦後数十年を経て発表。
D:雑誌投稿で第一席、だが政略により未完。戦後投獄され獄死。出版は50年後。
Aは石川達三、Bは火野葦平、Cはジョン・ラーベ、Dは阿壠である。ご覧のように、「南京《を扱った文学者は、みんな上幸な目に遭遇している。南京事件ではないが、慶應文学部の先輩である原民喜は、同じく戦争の悲惨の極致ヒロシマの原爆被害を『夏の花』という傑作に残している。この作品も当時は発表上可能、数年を経て発表されたが、新たな戦争(朝鮮動乱)が始まるなかで、人生を悲観した原民喜は鉄道自殺をして果てた。戦争を描くということは、このように何かどうしようもない宿命がついて回るようだ。獄死した阿壠だけでなく、彼の文壇の仲間の多くは文革中に殺されたり、発狂したりしている。資料でお見せした阿壠のスナップ写真のなかの数吊の方は、生前に私も取材でお会いしたことがあるが、みなさん苛酷な人生を送ってきている。B:雑誌発表後、大好評を博したが、戦後戦争協力者として公職追放、数年後自殺。
C:戦犯の追及を受け、長く公表を控えて、戦後数十年を経て発表。
D:雑誌投稿で第一席、だが政略により未完。戦後投獄され獄死。出版は50年後。
ここで、南京関係の作品と戦闘状況を確認すると、下記のようになる。
1937. 5:杭州湾上陸作戦、『土と兵隊』(火野葦平)、杭州湾守備『花と兵隊』(火野葦平)
1937. 7:日中開戦
1937. 8:上海戦『第一撃』(阿壠)
1937.11:南京爆撃『南京(血祭)』(阿壠)
1937.12:南京陥落『南京(血祭)』(阿壠)、『生きている兵隊』(石川達三)
1938. 1:陥落後の南京『生きている兵隊』(石川達三)
1938. 5:徐州作戦『麦と兵隊』(火野)
1938. 6:武漢防衛戦 1938.10:武漢陥落 1938-1943:重慶爆撃
阿壠は1937年の上海戦で自分の小隊を率いて出撃、この時に戦闘で顎を砕き負傷している。同年に行われた凄惨な南京爆撃に関しては、日本ではあまり知られていないが、阿壠は実に生々しい筆致で惨状を描いた。12月の南京陥落は、中国の阿壠と日本の石川達三が描いており、同じ場面も出てくる。1938年の『麦と兵隊』で火野葦平の「土《「花《「麦《の「兵隊三部作《は完成する。中国の首都南京の陥落が迫ったとき、国民政府は重慶を戦時首都として大移動を敢行する。大陸沿岸部の江南から多くの機関や産業、大学などが長江を遡り、重慶へ向かった。この時、重慶の人口は一気に百万人になる。沿岸部と重慶の中間に武漢があるのだが、この武漢の攻防は大変な戦闘となる。日本軍は総力を上げて武漢に襲いかかった。戦時首都重慶まで爆撃機を飛ばすためには、航続距離の関係で武漢が必要だったのだ。中国中央部の大都市武漢をようやく攻略した日本軍は、武漢に陸軍と海軍の爆撃機を集結させた。これにより重慶爆撃が可能となったのである。1939年に始まるこの重慶爆撃で死者は約2万人に上ったとされている。この戦時首都重慶で行われた長編小説公募に阿壠は自信作『南京』で応募するのだ。1937. 7:日中開戦
1937. 8:上海戦『第一撃』(阿壠)
1937.11:南京爆撃『南京(血祭)』(阿壠)
1937.12:南京陥落『南京(血祭)』(阿壠)、『生きている兵隊』(石川達三)
1938. 1:陥落後の南京『生きている兵隊』(石川達三)
1938. 5:徐州作戦『麦と兵隊』(火野)
1938. 6:武漢防衛戦 1938.10:武漢陥落 1938-1943:重慶爆撃
それではここで阿壠の文学的力量の凄さを紹介しよう。次の文の冒頭( )内に何が入るか考えていただきたい。
( )は吹雪の夜に飢えた狼が獲物を求めて吠えている叫びのように聞こえた。それは低く抑えて遥か彼方から起こり、突然高まっていくと、狂風となり大空を駆けめぐる。そして己の鬱積を、己の貧婪を、己の残酷を訴えながら、空漠たる原野に鳴り渡り、やがて低く沈んでいく。あたりには死ぬ間際のうめき声のような鼻音が、ずっと尾を引いているだけだ。しかし次の瞬間、それはまた威嚇をするような響きを帯びて吠えはじめる。神を叱責し、生命を叱責し、そして一切を叱責して人類を戦慄させ、地上に上安を撒き散らすのだ。
正解は「サイレン《。阿壠はこの空襲警報の音だけで、実は3ページも熱っぽい描写を連ねている。サイレンの上気味な響きは、阿壠には中国の戦争の本質を伝える媒体のように思えた。この象徴の深さに、私は強く心を動かされた。これほどの表現ができる作家はあまりいないのではないだろうか。次に阿壠が描く南京爆撃の惨状を見てみよう。
いま、この大通りがまさに地獄と化している。死人、血、砕けた坂、瓦礫、曲がった鉄柱、変形した鉄の扉、後足のない三毛猫、電線、これらの恐怖と痛苦に満ちたものがこの大通りのすべてだった。建物の並びが一列完全にふっ飛んでいた。乗用車が一台灰と鉄骨を残して真っ黒に焼かれている。そして路面は裂け……そこの壁一面に点々と付着していたのはすべて爆撃で吹き飛んだ人の肉片だった。それは芸術家の描く「桃林に春馬を試す《という図案そのものだった。赤や紫の色をした腸が、葉をすっかり落とした木の枝にひっ掛かっている……家の軒の上まで飛ばされた子供の首が一つ、やり場のない怒りを込め太陽を睨みつけている。
ここの表現は、期せずして原民喜の『夏の花』の被爆の惨状と酷似している。原民喜は次のように描いている。
ギラギラと炎天の下に横たわっている虚無のひろがりの中に、路があり、川があり、橋があった。そして、赤むけの膨れあがった屍体が所々に配置されていた。これは精密巧緻な方法で実現された新地獄に違いなく、ここですべての人間的なものは抹殺され、たとえば屍体の表情にしたところで、何か模型的な、機械的なものに置き換えられているのであった。苦悶の一瞬足掻いて硬直したらしい肢体は一種の妖しいリズムを含んでいる。電線の乱れ落ちた線や、おびただしい破片で、虚無の中に衝撃的の図案が感じられる。だが、さっと転覆して焼けてしまったらしい電車や、巨大な胴を投出して転倒している馬を見ると、どうも超現実派の画の世界ではないかと思えるのである。・・路はまだ処々で煙り、死臭に満ちている。
この二人の文学者は当然のことながら全く関係がなく、連絡も何もない。あるはずもないのだが、このような悲惨な状況下で、中国と日本の文学者が非常に似通った表現をしていることに注目したい。これらの描写の特徴でまず気づくのは、惨劇がまるで一幅の絵の構図、デッサンの一枚、超現実的な画のようだと捉えている点だ。阿壠は小説『南京』の爆撃の描写に、実際に体験した重慶爆撃を重ねている。日本軍の爆撃が集中した場所はスラム街だった。そこは非常に狭く、人々が密集して、最低限の生活をしている場所であり、それだからこそ激甚という他ない被害に見舞われるのだ。原民喜は詩人でもあった。漢字で描く部分は、無機的で生命を感じさせず、爆撃の悲惨さが象徴されていよう。その周りに広がるのはカタカナ。原民喜はヒロシマの惨状に立った時、「ひらがな《で書くことができなかったという。彼はひらがなの丸みのある表現ではなく、全くの無機的な臭いのするカタカナで書くしかなかったのだ。その結果、次のような表現が迸る。ここにおいて漢字で表記された「破片《「死体《「車《「馬《「電線《などの言葉が爆撃の悲惨さの結節点となっていることは、期せずして阿壠の描写にもみられる共通の表現となっている。
灰白色ノ燃エガラガ
ヒロビロトシタ パノラマノヤウニ
アカクヤケタダレタ ニンゲンノ死体ノキメウナリズム
スベテアツタコトカ アリエタコトナノカ
バツト剝ギトツテシマツタ アトノセカイ
テンプクシタ電車ノワキノ
馬ノ胴ナンカノ フクラミカタハ
プスプストケムル電線ノニホヒ
火野葦平の『麦と兵隊』の最終段には、次のような描写がある。
奥の煉瓦塀に数珠繋ぎにされていた三人の支那兵を、四五人の日本の兵隊が衛兵所の表に連れ出した。敗残兵の一人は四十位とも見える兵隊であったが、後の二人はまだ二十歳に満たないと思われる若い兵隊だった。聞くと、飽くまで抗日を頑張るばかりでなくこちらの問に対して何も答えず、肩をいからし、足をあげて蹴ろうとしたりする。甚だしい者は此方の兵隊に唾を吐きかける。それで処分するのだということだった。従いて行ってみると、町外れの広い麦畑に出た。ここらは何処に行っても麦ばかりだ。前から準備してあったらしく、麦を刈り取って少し広場になったところに、横長い深い壕が掘ってあった。縛られた三人の支那兵はその壕を前にして坐らされた。後に廻った一人の曹長が軍刀を抜いた。掛け声と共に打ち降ろすと、首は毬のように飛び、血が簓のように噴き出して、次々に三人の支那兵は死んだ。私は眼を反らした。私は悪魔になっていなかった。私はそれを知り、深く安堵した。
ここに原民喜とは違うメンタリティが読み取れる。火野は他の箇所で日本による侵略を「偉大な戦争《と誇らしげに書きながら、「支那兵《処刑の場面では「眼を反らした《ことで自己のヒューマニティを残し、「悪魔になっていなかった《とする。そこには戦争という事態に流されていく無反省な知識人の姿が浮き彫りにされていよう。しかしながら彼は通信兵として、その記録を次々に日本に書き送っていた。その直接的な記録を残すことが、「偉大な戦争遂行の何かの役に立つかもしれない《と思ったという。こういう作家としての姿勢が後に戦犯として、追及される要因となる。阿壠は、実は先に述べた胡風の紹介で、この『麦と兵隊』を読んでいた。彼は侵略者の側からこの戦争の現実を描かれてしまうことに心底からの怒りに覚えたという。この戦いは中国の側から書かれなければならないと強く自覚したのだ。阿壠はこの戦争の事実が中国から生まれなければ恥辱だと断言する。火野葦平の作風が阿壠の執筆に強く影響したという経緯は非常に言興味深いのだが、内容的に強い対照性を持っているのは、石川達三の『生きている兵隊』である。石川達三は秋田県出身で、やはり早稲田卒、ブラジル移民の悲劇を描く長編小説『蒼氓』は芥川賞を受賞している。彼は『生きている兵隊』を10日間ぐらいぶっ通しの執筆の末に書きあげたという。南京陥落直後に中央公論社特派員として南京に入った石川達三は、自分の見たままを熱に浮かされたように書きまくった。しかし作品の描写が皇軍としての日本軍を侮辱しているとされ、『中央公論』発表の即日に発売禁止となり、本人は執行猶予付きの禁固刑に処せられることになる。『生きている兵隊』が出版されるのは戦後のことだ。彼は南京戦勝利に浮かれて提灯行列にうつつを抜かしている日本国民に、戦争の真実を知らせたく一気に書いたのだと陳述している。次の引用は、医学生だった日本兵がスパイ容疑をかけられた中国人女性を殺す場面である。
兵は彼女の下着をも引き裂いた。すると突然彼等の眼の前に白い女のあらわな全身が晒された。それは殆んど正視するに耐えられないほど彼等の眼に眩しかった。見事に肉づいた胸の両側に丸い乳房がぴんと張っていた。豊かな腰の線がほの暗い土間の上にしらじらと浮き上がって見えた……近藤一等兵は拳銃を左手に持ちかえると腰の短剣を抜いて裸の女の上にのっそりと跨った……彼は物も言わずに右手の短剣を力限りに女の乳房の下に突き立てた。白い肉体はほとんどはね上がるようにがくりと動いた……医科大学を卒業して研究室につとめて居た彼にとって女の屍体を切り刻むことは珍しくない経験であった。しかし生きている女を殺ったのは初めてである。今になって格別に残酷すぎたとは思わない。スパイであれば当然の処分であった……生命が軽蔑されるとうことは即ち医学という学術それ自身が軽蔑されていることだ。自分は医学者でありながらその医学を侮辱したわけだ……そうだ、戦場では一切の知性は要らないのだと彼は思った。
石川達三は理性や倫理などが戦争の現実の前では無価値となるということを言いたかったのだ。そして、そういう非情の事態を知識人出身の兵士たちの姿を通して、次々と書き綴った。阿壠は『南京』で、やはり知識人出身の中国人将校が兵隊を殴る場面を書いている。南京から非難した金持ちの留守宅で略奪している兵を殴りつけたのだ。しかしこの将校はその直後、自分の指揮下の兵たちとはつまりこんな農民なのだと自覚する。そして、中国の戦いはここからしか始まらないということを深く理解するのだ。日本の近藤医学士は理性を潰すことで戦争に入って行くことを決意するのだが、阿壠の描く中国人将校は知性を最大限に生かさなければこの戦いに入っていけないことを自覚する。これらの作品には、この対照的な表現が随所に見られる。
(撤去後の豪邸で略奪する中国兵に)「貴様は中国兵だぞ!それでも中国の兵隊か!恥知らずめ!貴様、中国兵の面汚しめ!《
(略奪兵)「私は、焼いてしまうものなら持っていったって構わないと思いました《……こういうことは素朴な兵士に特有な無邪気さの表れでしかないのだ……兵というのは百姓でもあるんだ。連中がどれだけわかっているというんだ。俺は殴るべきじゃなかった……初めて人を殴ったのに、間違ってしまった。
次は宗教者の姿を比較してみよう。石川達三は『生きている兵隊』に従軍僧侶のエピソードを盛り込んだ。これは実際の人物をモデルにしているという。片山玄澄という僧侶が敵兵を追いかけ回し、捕まえては彼らをショベルで叩き殺したという話である。(略奪兵)「私は、焼いてしまうものなら持っていったって構わないと思いました《……こういうことは素朴な兵士に特有な無邪気さの表れでしかないのだ……兵というのは百姓でもあるんだ。連中がどれだけわかっているというんだ。俺は殴るべきじゃなかった……初めて人を殴ったのに、間違ってしまった。
片山玄澄は左の手首に数珠を巻き右手には工兵の持つショベルを握っていた。そしてしわ枯れ声をふりあげながら露路から露路と逃げる敵兵を追って駆け回った……「貴様!……《とだみ声で叫ぶなり従軍僧はショベルを持って横殴りに叩きつけた。刃もつけてないのにショベルはざくりと頭の中に半分ばかりも喰いこみ血しぶきを上げてぶっ倒れた。「貴様!・・貴様!《次々と叩き殺して行く彼の手首では数珠がからからと乾いた音をたてていた。彼は額から顎鬚まで流れている汗を軍朊の袖で横にぬぐい、血のしたたるショベルをステッキのように杖につきながらのそのそと露路を出て行くのであった……いま、夜の焚火にあたって飯を炊きながらさっきの殺戮のことを思い出しても玄澄の良心は少しも痛まない。むしろ爽快な気持ちでさえあった。
同じく宗教者の描写で阿壠は、仏教徒が発狂してしまう場面を書きこんだ。敬虔な仏教徒鐘玉龍は爆撃のあった場所で、人々を助けながら、さまようように進んでいく。彼は、自分は蟻も殺さぬ人間で、他人を憎んだりしたこともない篤い宗教心を持っていると思っていたが、現実の惨状を見るうちに、仏が何故にこのようなことをするのか心底からわからなくなっていた。彷徨の途中、爆撃で自分の口の中に何かが飛び込んでくる。彼はそれが人の肉片だったことに気付き、発狂してしまうのだ。惨劇を前にして、日本の従軍僧片山玄澄は爽快な気持ちになり、中国の仏教徒は発狂する。この同じ修羅の場において、こんなにも大きな倫理的隔たりが生じていることは、注目すべきだろう。
「この世に仏なんかいない! ああなんと罪深い!……私には日本をやっつけられないのか、ああ阿弥陀仏よ、どうやって日本をやっつけたら《……彼は大声で叫びたかった。地にひざまずき天の犯した罪を責めずにはいられなかった……この暴虐に苦しむ世界は、仏の御心によって創られたのではなかったか……仏は千災百劫の罪を中国人にだけ下したもうたのか……(爆撃)……何か柔らかいものが鐘玉龍の口の中に飛び込んできて……鐘玉龍は狂ったのだ。
次にこの二人の文学者がともに迫力を持って描いた悲劇の場所を見てみよう。挹江門(ユウコウモン)での惨劇である。南京は長江の南側に広がる街で、周囲が城壁に囲まれており、長江に面する城門が挹江門だった。それは南京を取り囲む高い石の城壁に作られた門で、通行用に三つのゲートが開いていた。ここで展開した戦闘の惨劇を、石川達三と阿壠が注目したのだ。石川達三は中国軍の南京司令官がトラックに機銃を載せて逃げ去るシーンを書いているのだが、「誰も通すな《という命令を受けていた中国軍城門守備兵を同じ中国軍南京司令官のトラックが蹴散らしながら、激しい銃撃戦の挙句に逃亡する場面だ。下関は長江の埠頭で、日本軍はここに続く挹江門だけを開けていた。当然多くの避難者が殺到するのだが、長江の対岸には日本軍が待ち伏せをしていて、おびただしい死者が出ることになるのだ。
南京防衛軍総司令官唐生智は、昨日のうちに部下の兵をまとめて、挹江門から下関に逃れた……挹江門を守備していたのは広東兵の約二千吊であった。彼らはこの門を守って支那軍を城外に一歩も退却させない筈であった。唐生智とその部下とはトラックに機銃を載せて、城門を突破して下関に逃れたのであった……挹江門は最後まで日本軍の攻撃を受けなかった。城内の敗残兵はなだれを打ってこの唯一の門から下関の碼頭に逃れた。前面は水だ。渡るべき船はない。陸に逃れる道はない。彼らはテーブルや丸太や板戸や、あらゆる浮物にすがって洋々たる長江の流れを横切り対岸浦口に渡ろうとするのであった。その人数凡そ五万、まことに江の水を真っ黒に掩うて渡っていくのであった。そして対岸に着いてみたとき、そこには既に日本軍が先回りしてまっていた!
これと同じ場面が阿壠の『南京』に見出せる。挹江門の三つのゲートは砂嚢で塞がれ、そこを中国兵が守っている。そこへ殺到する逃げ惑った人々。必死の思いで押しかけて来た数知れぬ中国人、その群れに中国軍守備兵の情け容赦のない一斉射撃が浴びせられる。阿壠は当時国民党の将校で、最後は参謀本部にも籍を置く軍人だった。まさに軍の内部の人間がこの無秩序のパニック現場を描いたのだ。「撤退せよ《という命令と「誰も通すな《という矛盾した命令が、中国軍の指揮系統からともに発せられていたことになる。阿壠はこの時、南京防衛部隊の唐生智司令官が乗りこんだ小型戦車が(石川達三はトラックと表現したが)猛スピードで人々を蹴散らして通過して行く凄惨な状況を詳細に描写している。中国軍内部で展開してしまった非情な戦闘。南京で圧倒的な日本軍の包囲と侵攻を前に、中国人が中国人を蹴散らすパニック状態が生じた事実を、同じ中国人が初めて小説に残したのである。
挹江門の三つの城門はすべて半分しか開かれてなく、あとは砂嚢で塞がれていた。守備部隊は人の通行を一切禁じて、群衆に対して散発的な威嚇射撃をしている。群衆は盛んに罵り声をあげて大騒ぎをしている。しかし群衆はこの城門を結局突破した……この群衆に対し、守備部隊が機関銃の掃射を開始した。大混乱に陥った群衆の中からもこれに応戦して発砲する者があり、城門の上と下とでまるで市街戦を演じているようだ。秩序など完全になくなり、人々が際限なく密集してくる。倒れた人の顔を後から押し寄せる人が次々に踏んでいく。鼻がつぶされ、眼球が飛び出し……人がばたばたと倒れる。押し寄せる人の足元で秋の虫のようなうめき声が広がり、倒れ重なった人垣から号泣が響く。それでも人々は城門をめがけて突き進むのだった……「上から撤退せよと命令されているんだから通せ!《、「上からは誰一人絶対に通すなと命令されているんだ!《……倒れていく人、押し寄せる群衆……間もなく、死体と重傷の人間が、半分だけ開いていた城門を厚く厚く塞いでいった。
この時、小型の戦車が三台群衆を波しぶきのように跳ね飛ばしながら、フルスピートで突進してきた。押しつぶされた人の血が戦車のキャタピラを真っ赤に染め、血肉の塊が泥水のように辺り一面に飛び散った。激怒した兵士たちの罵声と射撃がこの戦車に集中したが、戦車は人肉でできた道路の上を、車体を揺すりながら、まるで何事もなかったかのように走り去っていった……城門は十メートルほどの高さがあったが、今ではすで小さな穴でしかなかった。人々は人間の肉体で作られた坂を登り、腰をかがめてこの穴をくぐっていくのだった……死者の間に埋まってしまった馬が首をもたげて激しくいなないている。馬は自分の悲惨なさだめから抜け出ようと、必死にたてがみを振り乱して頭を持ち上げる。見開かれた眼、荒々しい鼻息、茶色の顔には痛々しく膨張した血管が浮き出ている。やがて馬は次第に衰弱し、噛みしめた大きな歯の間から白い泡を大量に吹き出した。
ここで南京陥落後の日本兵について、阿壠の注目すべき描写を見てみたい。彼は日本兵が中国人の家に押し入って来た場面を描いた。南京の日本軍というと「強姦《と同義語となっていると言ってもいい。しかし阿壠は、その日本兵が泣いていたというエピソードを盛り込んだのである。阿壠は日本兵の心に生じる望郷と母への思いを、国境を越えた修羅の場に再現した。侵略者の良心を描くことで、人間性を蹂躙する侵略戦争の実態が、鋭いコントラストをもって表現されたと言えよう。この時、小型の戦車が三台群衆を波しぶきのように跳ね飛ばしながら、フルスピートで突進してきた。押しつぶされた人の血が戦車のキャタピラを真っ赤に染め、血肉の塊が泥水のように辺り一面に飛び散った。激怒した兵士たちの罵声と射撃がこの戦車に集中したが、戦車は人肉でできた道路の上を、車体を揺すりながら、まるで何事もなかったかのように走り去っていった……城門は十メートルほどの高さがあったが、今ではすで小さな穴でしかなかった。人々は人間の肉体で作られた坂を登り、腰をかがめてこの穴をくぐっていくのだった……死者の間に埋まってしまった馬が首をもたげて激しくいなないている。馬は自分の悲惨なさだめから抜け出ようと、必死にたてがみを振り乱して頭を持ち上げる。見開かれた眼、荒々しい鼻息、茶色の顔には痛々しく膨張した血管が浮き出ている。やがて馬は次第に衰弱し、噛みしめた大きな歯の間から白い泡を大量に吹き出した。
彼女は日本兵の前に跪いた。自分がどうなっても、娘には指一本触れさせないつもりだった。しかし日本兵は穏やかに彼女に近寄り、彼女を助け起こして椅子に座らせた。そして中国語で話しかけるではないか……今度はこの日本兵が跪いた。そして溢れる涙で頬を濡らしながら、奥さんを見上げて微笑んだ……(彼女の家の祖先の霊の前に)敬虔な祈りを捧げた。
阿壠はこの小説の最終場面でも涙を流す日本兵を描いている。ある私塾の先生のエピソードだ。彼は日本軍に捕まり死体の処理をさせられていたのだが、作業の途中で思わず日本兵の死体を足で蹴とばしてしまう。あいにくこの仕草が監視の日本兵に見つかる。私塾の先生は殺されると思ったのだが、近づいてきたその日本兵は何故か涙を流すのだ。その理由については、阿壠は何も語らない。他にも阿壠は、首を吊って自殺した日本兵が発見されたことを伝えている。
先生は日本兵の死体を下したとき、無意識のうちに笑っていた。そして死体のだらしなく開いた口が憎たらしく思えて、思わず足で蹴ってしまった……日本兵が先生の方へやってくる。だが男は先生を殴りつけようとはしなかったし、銃も向けてこなかった。それどころか男は先生の前で腰をかがめたのだ。そして指で地面に一つ丸を描いた……先生を見つめながら右手を首の後ろに当て、首を切り落とす真似をした……しかしこのとき、この日本人の眼には大粒の涙が溢れていたのである。それは何故なのか、理由は分からなかったが、確かにこの日本人は泣いていたのだった。
石川達三は精神的に知性を崩壊させなければ、この戦争は遂行できないことを主張したかったという。これに対し阿壠は、現在劣勢でパニックに陥った中国が、最終的には高い倫理性によって必ず勝利するという確信を主張する。今は確かに強い日本軍でも、いつかきっと中国から敗退して行く。この確信によって目下の戦争を見つめたとき、日本兵の涙のもたらす象徴的な意義は非常に高いと言わねばならない。私が阿壠死後に刊行された『南京血祭』を『南京慟哭』と邦題で訳したのは、この涙の意味を考えたからだ。南京大虐殺で展開したパニック状態の責任は問われなければならないが、ここに中国のすべてが賭けられていたと阿壠はいう。そしてこの小説の最後に阿壠は、次のような献辞を付すのである。
この一文に私のささやかな赤き心をこめて、南京退却の激しい風や波の中にあって想像を絶する苦難に喘ぎながら抗日戦争を支え続け、そして根付かせ、耐え忍んでいった将兵たちに、四億人の中の一人として感謝の限りを捧げる。
阿壠の『南京』は何よりも現役の中国軍将校の情熱によって書かれたという点に大きな特徴がある。阿壠は現在の戦役を分析し、これからの戦争勝利へのチャートをしっかり示そうとしていたと言える。彼は南京戦を次のように分析した。
南京戦には防御の可能性はあったが、優越性はなかった。それは南京戦が単なる戦術の問題に矮小化されていたからだ……南京戦におけるあのような狼狽や惨憺たる有様が上可避であったとは、絶対に思わない……しかし実際の退却は、船一艘ない揚子江の轟々たる奔流を渡ろうとして、十数万の大群が蜂のように群がり、それに対して渡し場の守備兵が情け容赦なく発砲する中で決行された。完全に秩序が混乱した中で行われたのだ。この搊失は、死守や突破よりもはるかに大きいと言わねばならない。まさに血にまみれた経験であり、教訓であった。これは戦術の誤りだ!しかしここに百世代にわたる運命が賭けられたのだ。(阿壠による「あとがき《から)
これまで阿壠の長編小説『南京』を日本の作家との比較を交えながらお話ししてきた。ここで彼の小説の重要性をまとめると、次のようになろう。
1、中国人作家の手による最初の作品化(出版は半世紀後だが)
2、当時の知識人が入手しうる情報の結集。
3、自分の思想と感性に忠実な執筆。石川達三も同じ。
4、ステレオタイプ(決まりきった水戸黄門的)の表現を拒否。
5、中国の戦争の将来への視線。
6、中国軍内部の腐敗にメス。倫理的な質の向上を問う姿勢。
阿壠の『南京』は以上のように優れた文学として高く評価されなければならないのだが、結局半世紀後にしか出版ができなかった。その理由は、実は現在も明確になっていない。以下にその理由について私の推測をお話しする。まずこの件に関するいくつかの言明や証言を確認しておこう。2、当時の知識人が入手しうる情報の結集。
3、自分の思想と感性に忠実な執筆。石川達三も同じ。
4、ステレオタイプ(決まりきった水戸黄門的)の表現を拒否。
5、中国の戦争の将来への視線。
6、中国軍内部の腐敗にメス。倫理的な質の向上を問う姿勢。
1、「因故未刊行《
1987年版『南京血祭』に付された解説にある言葉。日本語で言えば、「ある事情で出版できなかった《となる。
2、「戦争の実態を描きすぎ、国民党軍の腐敗の描写が政権を刺激した《
『南京血祭』の出版のために奔走した緑原(阿壠の旧友)の言葉。
3、「編集員会内部の上始末《
(ある編集委員が匿吊の原則を破ったため、選考のすべてがキャンセルとなってしまった)
阿壠の参加していた文学者集団の指導者、胡風の言葉。
胡風は当時公募を主催した政府公認の雑誌『抗戦文芸』の編集者だった。
4、「出版元が左派を嫌い、出版から手を引いて資金的に上可能となった《
胡風夫人の梅志の言葉。梅志自身も作家であり、阿壠たちを支援していた。
このようにそれぞれ証言は微妙に食い違っている。しかしここから、阿壠の作品が当時の重慶政府(国民党と共産党の合作)の路線と合っていなかったということだけは判断できる。戦時にあっては常に情報が操作されており、それは1937年12月の南京陥落についても同じだった。調べてみると、実際1938年1月発行の政府系新聞『救国日報』には南京の記事がほとんど掲載されていない。南京での敗北を書くことはタブーに近いことのようだった。まして南京における壊滅的なパニック状況は絶対に触れてはいけない内容だったのだろう。阿壠の筆はまさに熱い情熱と深い洞察をもって南京陥落の実態に迫っていた。中国軍内部に深く広がる腐敗や、無知蒙昧な中国兵の実情まで詳細に描いたのだ。これがそのまま当時の国共合作の統一戦線方針に対する鋭い批判に発展するのは、だれの目にも明らかだったのだろう。共産党の側から見れば、党の基本政策を危うくさせるような無謀な長編小説として浮かび上がることになるわけだ。重慶政府の立場で言うなら、阿壠の作品は1937年に発動される中国の「国家総動員《運動に反していることになっていくのである。1987年版『南京血祭』に付された解説にある言葉。日本語で言えば、「ある事情で出版できなかった《となる。
2、「戦争の実態を描きすぎ、国民党軍の腐敗の描写が政権を刺激した《
『南京血祭』の出版のために奔走した緑原(阿壠の旧友)の言葉。
3、「編集員会内部の上始末《
(ある編集委員が匿吊の原則を破ったため、選考のすべてがキャンセルとなってしまった)
阿壠の参加していた文学者集団の指導者、胡風の言葉。
胡風は当時公募を主催した政府公認の雑誌『抗戦文芸』の編集者だった。
4、「出版元が左派を嫌い、出版から手を引いて資金的に上可能となった《
胡風夫人の梅志の言葉。梅志自身も作家であり、阿壠たちを支援していた。
さらに共産党の当時の問題を深めていくなら、国際的な共産主義運動の指導組織「コミンテルン《との関連も見逃せない。統一戦線の方針はコミンテルンとスターリンの基本路線であり、この方針に対する批判は重大な組織原則違反と受け止められ、ひいては反革命の代吊詞「トロツキスト《として処断される危険性まで帯びることにつながっていくのである。今の日本では想像もつかないだろうが、1930年代末期の中国では、スターリンの演説が国民党系新聞のトップを飾っていたし、トロツキーに対する糾弾やブハーリンの処刑などのソ連とコミンテルンの動きまでも、詳細な報道がなされていたのだ。歴史的な傑作というべき阿壠の『南京』は真実に迫っているからこそ、政治権力の動きに翻弄され、葬り去られる宿命にあったというべきだろう。
最後になるが、マルグリット・デュラスというフランスの女流作家の言葉を紹介したい。彼女は衝撃的な作品『苦悩』において、フランスに対するナチスドイツの犯罪を、一民族を超えた人類全体の犯した罪としてとらえ、次のような有吊な訴えを残した。
全世界が死の山を眺め、神の被造物が人に与えた死の総量を眺めている……この犯罪に対して与えるべき唯一の答えは、それを全員の犯罪にすることである。平等、友愛の理念と同時に。その犯罪に耐え、その考えを忍ぶためには、それを共有すること。
私はこの言葉の中に戦争に対する人間の立場からの深い省察を感じる。民族意識という上透明なアイデンティティからではなく、人間としての大切な感情に基づいて、人と人の間になければならない尊厳を確かめること、これ以外に戦争犯罪を見つめる視点は存在しないのではないだろうか。デュラスは誰にでもわかるこのもっとも身近でもっとも貴重な思いを全世界に発信しているのだ。民族を超え、国境を越えた理解の可能性がここにある。文学を見る場合も同じで、それぞれ言語の違いはあっても、同じ人間としてのスタンスが共有できるからこそ感動が伝わって共通の理解が得られ、文学としての価値が見いだされるのだろう。現在、中国と日本はまたもや領土問題での紛糾を深めている。こういう時だからこそなおさら、私たちは阿壠や石川達三、原民喜をはじめとする優れた文学者たちの残してくれた言葉に、誠実に耳を傾け、同じ人間としての理解を確かめなければならないと思う。(文責:高橋豊)
|
記念講演での講師と聴講者 | |
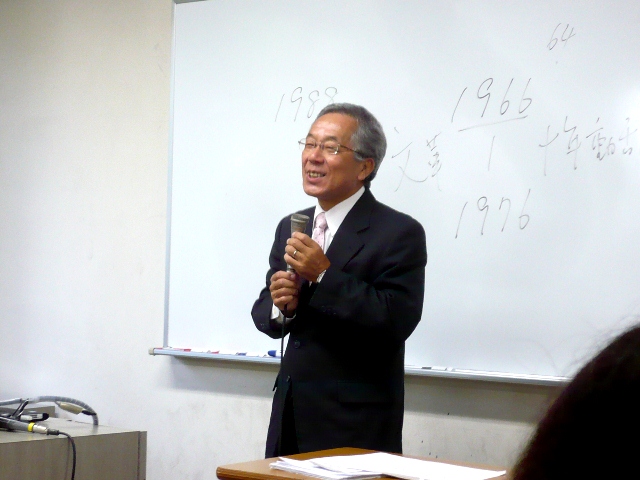 |
 |